政府は、2026年度を目途に正常分娩の出産費用を公的医療保険の対象とし、自己負担を原則無償化する方針を進めている。これは、少子化対策の一環として、妊婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えることを目的としている。
現行制度と課題
•現状:正常分娩は公的医療保険の対象外であり、出産費用は医療機関ごとに設定されている。帝王切開などの異常分娩は保険適用となっている。
•出産育児一時金:現在、一律50万円が支給されていますが、都市部では出産費用がこれを上回るケースもあり、自己負担が発生している。
•地域差:出産費用には地域差があり、東京都では約60万円、熊本県では約36万円と大きな開きがある。
保険適用の具体化に向けた検討
•給付形態の変更:出産費用の保険適用は、現金給付から現物給付への切り替えを意味する。これにより、医療保険者が医療機関と契約し、出産サービスを提供する形式となる。
•給付範囲の検討:分娩料、入院料、新生児管理保育料など、どこまでを保険給付の対象とするか議論されている。室料差額などは保険適用外とする案もある。
•診療報酬の設定:保険適用となる場合、診療報酬は全国一律に設定されるため、医療機関の経営への影響も考慮する必要がある。
懸念点と課題
•医療機関への影響:保険適用により診療報酬が現在の費用を下回る場合、医療機関の経営が悪化し、分娩対応が困難になる懸念がある。
•医療提供体制の確保:地域の周産期医療提供体制を維持するため、医療機関の実態を把握し、適切な制度設計が求められる。
•自己負担の設定:原則3割の自己負担が生じる医療保険制度で、出産費用をどのように無償化するかが課題となる。
今後のスケジュール
•2025年春:厚生労働省と子ども家庭庁の検討会で一定の方向性を示す予定。
•2025年末:診療報酬改定において、出産費用の保険適用に関する具体的な制度設計が進められる見込み。
政府は、これらの課題を踏まえ、妊婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えるため、出産費用の保険適用に向けた具体的な制度設計を進めている。


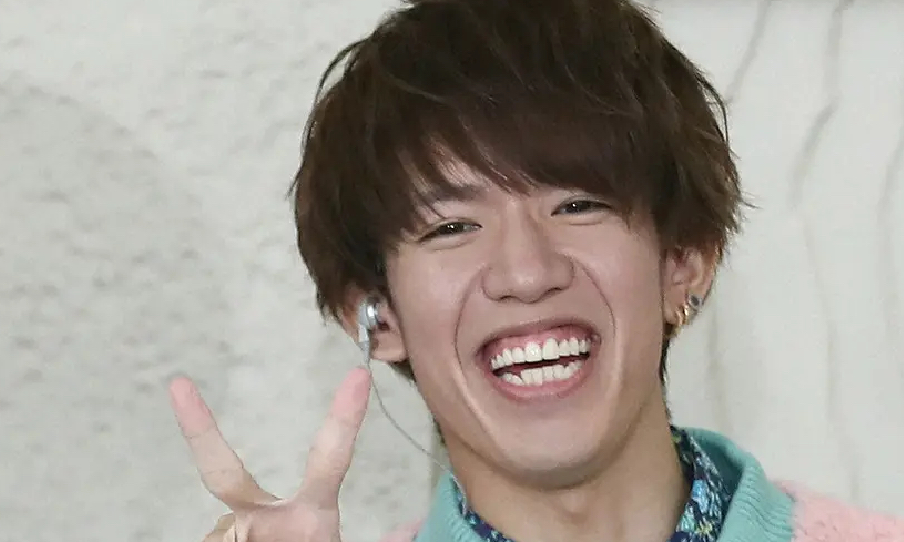
コメント